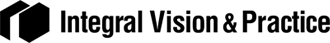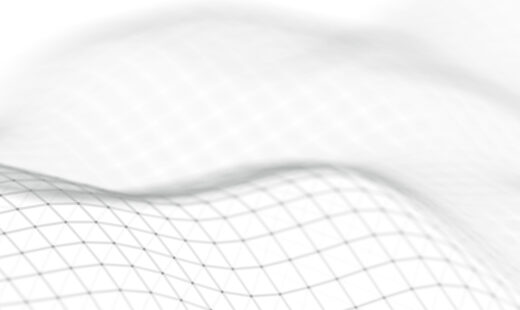映画「ソロモンの偽証」は最高の発達理論の教材


画像出典(松竹株式会社):ソロモンの偽証 前篇・事件 (shochiku.co.jp)
2015年に劇場上映された作品である。
遅ればせながら、DVDで鑑賞した。
前篇と後編を合わせると4時間をこえる作品となるのだが、一気に鑑賞してしまった。
残念ながら、素晴らしい前編とくらべると、後編は、間延びした構成と大仰な演技に足をすくわれて、作品として格段に落ちてしまうのだが、藤野 涼子や板垣 瑞生をはじめとする主演俳優達の優れた演技もあり、難しいことを言わなければ、素晴らしい時間を満喫することができるだろう。
個人的に観賞しながら思ったのは、「この作品は発達理論の教材として最高のものなのではないか」ということである。
具体的に言えば、「順応型段階」(Robert Keganのthird order)の呪縛をこえて、個人としての自律的な思考能力を獲得する「自己主導型段階」(Robert Keganのfourth order)を確立していく熾烈な葛藤がいかなるものであるのかということが、この作品の主人公の姿に実に見事に描かれているのである。
即ち、権威的存在によりあたえられた情報を無批判に受容して、それが「事実」であると、「真実」であると納得するのではなく、みずからの責任にもとづいて調査をして、真実に辿り着こうとする主人公達の思考と行動の中には、自己主導型段階という発達段階の尊厳が端的にあらわれているのである。
現代思想家のケン・ウィルバー(Ken Wilber)は、この発達段階を「夢をみることができる段階」と形容しているが、その言葉に籠められているのは、この発達段階がわれわれに自己の内に秘められている変革を生み出す能力に目覚めさせるということであり、それを発揮して世界に果敢に働きかけていくことを可能とするということである。
ある意味では、この作品の中で主人公達が協力して実践しているのは、巷で「探求学習」といわれる活動であるといえるが、彼等の活動が示唆するように、真の探求学習とは、正に現実世界そのものを大きく変えることになる。
それは真に批判的に問うことをとおして世界を規定する権威構造や支配構造を揺るがし、そうしたものを刷新する可能性を秘めているのである。
実際、作品には、こうした深い問いをはじめた主人公達を周囲の大人達が暴力を奮うことで妨害をしようとする光景がくりかえし登場するが、自己主導型段階に立脚して生きるとは正にそうしたリスクを引き受けることを意味するのである。
その意味では、探求学習とは、「従来の知識偏重型の勉強とは異なるあらたな能力開発の方法」というような単純なものではなく、本質的に社会的な意味と意義を内包する実践法といえるのである。
たとえば、ある教師は、主人公に対して、伝統的な学校行事である卒業文章の執筆に取り掛かるように主人公に強要をするが、それに対して、彼女はそうした活動が本質的に期待される綺麗言を並べたてた空虚な文章をとりまとめるだけの無意味な作業であることを訴えて反発をする。
こうした行動の中には、自己の内的な感覚に忠実(authentic)であることを最重要視して、たとえそれが権威的存在の指示や命令であるとしても、外部からの理不尽な介入に対しては決然と抵抗する意志を示す自己主導型段階の尊厳が端的に描かれているといえる。
特に文章の執筆とは、その個人の最も本質的な精神的活動に関わるものであり、その内容について他者が介入してくるのは、自己主導型段階(以降)に立脚した者にとっては、容認しがたい侵害行為と見做されることになる。
主人公は、そうした行為に対して違和感を覚え、その感覚を率直に表現するのである。
自己の内に生じた世界に対する違和感を誤魔化すことなく、それに声をあたえて表現をしていくこと――自己主導型段階の尊厳とは正にここにあるのである。
逆に言えば、少なくてもこの作品を眺める限りでは、現代の学校環境が、往々にして、自己主導型段階に向けて子供達が発達していくのを阻害する機能を果たしてしまう可能性が大いにあるということだ。
即ち、そうした発達の芽を摘み、子供達が順応型段階に留まりつづけるように条件付けしてしまうのである。
たとえば、非常に印象的な場面のひとつに、突然に校長が辞任したことを伝えられて動揺する生徒達の姿を見て、「校歌を斉唱して気持ちを入れ替えましょう」と壇上から教頭から生徒達に告げるというものがある。
当然のことながら、健全な感覚の持ち主であれば、組織長が突然に辞任すれば、その理由はどのようなものであるのかについて疑問を抱くであろうし、また、組織の責任者に対して説明を求めるだろう。
しかし、ここでは、歌を歌うという行為を気を紛らわせるための道具として用いることを通して、教師達は思考を停止させることを子供達に強要するのである。
そして、そのことを通して、そもそも問いを抱き、それについて考えることそのものを間接的に思い留まらせるのである。
自己主導型段階の特徴のひとつが、みずから問いを立て、それにもとづいて探求をしつづける知的持久力を発揮することであるとすれば、こうした「指導」は正にそれを妨害することであるといえるだろう。
また、この作品の中では、人間の発達において「勇気」が非常に重要な役割を果たすことが明確に示されていることも銘記されるべきであろう。
前編の後半、主人公は、同級生が「不審死」したことに関して大人達が説明責任を果たそうとしないことに憤り、みずからの責任において真相解明の活動を展開していくことを決意するわけだが、そこで大きな役割を果たしたのが、不審死した同級生が遺した批判の言葉である。
即ち、普段は大人達に期待される役割を果たしながら優等生として振舞っている自身の偽善性を指摘する辛辣な言葉を受け留めて、そこに息づく凶暴な真実の刃を自己に向けて苦悶することができたことが、最終的に世界に対して果敢に働きかけていくという責任を発揮する勇気を喚起することを可能としたのである。
換言すれば、自己の内に存在する矛盾を隠蔽することなく、それを事実として受け留めて、それを己の責任において解決することを決意するところに、この主人公の人格的な成長が生まれるのである。
自己主導型段階の意識にもとづいて行動を興すことが、周囲の関係者の反発を招くであろうことは、主人公は百も承知していることだろう。
しかし、彼女の中には、そうした外部の関係者による反発や弾圧にもたらされるものよりも耐え難い「痛み」があるのである。
それは、自己の人格の中に大きな矛盾を抱えたまま偽善者として生きることである。
彼女にとり、そうした生は生きるに価しない生なのである。
その意味では、そうした内的な葛藤を経験して、それに真摯に苦悩できることそのものが途轍もない能力であるといえるのである。
ここで非常に重要なことは、この作品に丁寧に描写されているように、こうしたあらたな意識を涵養するためには、周囲の関係者の支援が重要になるということである。
たとえば、この作品には、主人公達の自律的な探求を妨害しようとする大人達が数多く登場するが――その中には、たとえば小日向 文世が演じる教師や田畑 智子が演じる警官をはじめとして「善意」にもとづいた者達も含まれる――いっぽうでは、松重 豊が演じる教師等、少数の支援者が登場して、主人公達の中にめばえはじめた自己主導型段階の意識が、権威や制度に蹂躙されることなく、健やかに育つことができるように様々な支援を提供する(こうした姿勢こそが、真の発達志向型支援を特徴づけるものといえるだろう)。
自己主導型段階の意識は、本質的に、あたえられた「真実」を無条件に受容することを拒絶して、全てをみずからの精神にもとづいて再検証をする意識である。
そして、それゆえに、既存の権威や規範や構造や制度と対峙して、それらの妥当性や正当性に問いを投げかけるものである。
換言すれば、それは世界や社会に流動性をもたらす意識といえるのである。
しかし、それゆえに――正に人類史を通じて今日に至るまで繰り返されてきたように――そうした意識は弾圧や排斥の対象とされることになる。
また、われわれは人格形成の過程を通じて、そうした弾圧や排斥の存在を社会の所与の条件と受け容れて、それと共存することを大人の知恵としてとらえるように条件付けされてしまうことになる。
この作品においては、主人公達の果敢な態度に触発されて、長年にわたりそのように条件付けされてきた結果としてみずからがしらずしらずのあいだに自己主導型段階の意識を抑圧する役割を果たしていたことに気づいた少数の大人達が、彼等に支援の手を差しのべるが、そうした支援は、主人公達の発達論的な挑戦が実を結ぶためには、必須の条件となるのである。
また、こうした世代間のダイナミクスを眺めるときにあらためて気づかされるのは、既存の社会に過剰適応した大人達を救済するのが、ときとして、そこに適応することを拒絶する次世代の若者であるということである。
そうした「不適応者達」を適応に向けて強制的に「指導」「矯正」してことは可能かもしれないが、そうした「善意」の行動をとおして、大人達はみずからを救済する術を放棄してしまうことになるのである。
この作品が優れているところは、それが主人公達の発達の物語であるだけでなく、彼等を支援する大人達の救済の物語でもあるということである。
前編では、藤野 涼子が演じる主人公が学校や警察の方針に違和感を抱き、そうした問題意識にもとづいて行動を興そうとすると、母親(夏川 結衣)が、「そうしたことをすると教師達に目をつけられて内申書に不利なことを書かれることになるので、止めたほうがいい」と警告を発するする場面がある。
こうした言葉を聞くと、子供達は、内申書を人質にとられて、口を封じられている囚人に近い状態に置かれているといえるのではないかとさえ思われるのだが、母親は、物語の後半、こうした言葉が――たとえそれが愛にもとづいたものであるとしても――娘をひとりの人格的存在として尊重するまなざしを欠いたところに生まれたものであることを自覚して態度をあらためることになる。
そうした適応を強いる言葉が実質的に娘を「牢獄」に閉じ込めることになることに気づくのである。
そうした自覚は正に彼女自身の救済となるのである。
ところで、ひとつ面白いのは、西村 成忠が演じる準主人公が、物語のクライマックスを飾る裁判が終わると、瞬く間に気持ちを切り替えて受験勉強に向けて邁進していくことだ。
ある意味では、この人物はこの作品の中で最も優秀な頭脳をもつ人物として登場するが、残念ながら、その「優秀さ」には、自身が牢獄に囚われていることを自覚して、そこから自由になるための思考をしようとする発想は欠けているようである。
ある意味では、この作品に登場する人物達の中でも最も残念な人物といえるかもしれない。
このあたりに作品に籠められた辛辣な批判精神を認めることができるのである。
また、もうひとつ印象的なのは、作品を通して、生徒達があまりにも頻繁に教師達に御辞儀をさせられることだ。
作品中の描写がどれほど現実を反映しているのかは判らないが、その頻度は異様なほどである。
そうした仕草は途轍もなく空虚なものであり、その光景には、正にフーコーが指摘したように、権威に対して身体的レベルにおいて自動化された従順性の痕跡を見るような気がする。