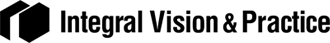インテグラル理論の視点から映画を語る インテグラルシネマ 第1回「スタンド・バイ・ミー」(Stand by Me, Rob Reiner, 1986)

あらすじ:1959年のオレゴン州の田舎街を舞台にして繰り広げられる4人の少年達の冒険譚。12歳の主人公の少年(ゴーディー・ラチャンス)と親友のクリス・チェインバース、そして、二人の仲間テディ・ドゥシャンプとヴァーン・テスィオは、失踪した少年の死体が街外れにあるという情報を偶然に入手し、死体発見者として街の英雄になろうと、出発していくのだった。
思春期において、われわれがひとりの個としての人格を確立するための一歩を踏み出そうとするときに経験することになる心の旅を詩情豊かに描いた1980年代の秀作である。公開後40年近い時間が経過しているにもかかわらず、少しも古びることなく、未だにわれわれ視聴者の心に郷愁の念と共に静謐な感動を呼び起こしてくれる。正に時の試練を生き延びた古典といえるだろう。
ところで、この作品はもちろん純粋な娯楽作品として鑑賞しても存分にたのしめるのだが、発達心理学のレンズを通して眺めても、豊かな示唆をもたらしてくれる。
端的に言えば、「順応型段階」(3 order)といわれる発達段階の呪縛を超えて、「前期合理性段階」(3.5 order)といわれる発達段階に向けて成長していく過程において、われわれが直面することになる苦悩と幸福と葛藤に関して深い洞察をもたらしてくれるのである。それは、それまでに「全て」を共にしてきた友を「喪失」する寂しさであり、また、真に自己をひとりの個として認識してくれる理解者を獲得する喜びである。
それは、また、それまでに世界の残酷な現実から自己を守ってくれた存在の権威が失墜する幻滅をあじわうことであり、また、そうした存在の保護を離れて、死に象徴される厳然とした生の現実に直接に触れるための勁さを得ることである。
思想家のケン・ウィルバーは、人間の成長とは「無意識的な地獄」を脱して、「意識的な地獄」に到達することであると述べているが――即ち、自らが地獄に生きていることに無自覚な状態を卒業して、そのことを意識できるようになることこそが人間の成長であるということだ――こうした段階的な成長の只中において、われわれは正にそうした気づきを得ることになるのである。
この作品の原作は、スティーヴン・キング(Stephen King)による『死体』(The Body)という短編小説だが、その題名に示されているように、この作品には死の主題が一貫して流れている。
作品の冒頭、主人公のゴーディー・ラチャンス(Wil Wheaton)は、自身の最良の理解者である最愛の兄を交通事故で失い、その死の影を背負う少年として登場する。また、両親は、兄の突然の死に精神的に完全に打ちのめされてしまい、主人公に対して愛情を向けることが全くできない状態に陥っている。こうした事情もあり、主人公は、密かに「死ぬべきは、誰からも愛された兄ではなく、この変わり者の自分だったのだ」という想念に囚われて、悪夢に魘される日々を送っている。換言すれば、主人公は、物理的に愛する兄を失っただけでなく、両親までも精神的に失ってしまったのである。
それまであたりまえのものとして存在していた家庭の平穏は、「死」によって瞬時に破壊されてしまい、主人公は突然に孤独の中に投げ出されてしまうことになる。
主人公は、たとえどれほど揺るぎないものにみえる生の輝きも、家族の結束も、この世界の残酷な現実のまえには瞬時に打ち砕かれてしまうことを直観すると共に自らが窮極的には独りでこの生の現実と直面することを求められていることを悟るのである。
順応型段階とは、共同体の中でひろく共有されている「物語」や「神話」を信奉して、その庇護のもとに精神的な平安を得る発達段階であるといわれる。
そうした物語や神話を「対象化」することなく、それを所与のものとして生きることこそが、過酷な生の現実から自己を守るための方法であることを無意識のうちに理解しているのである。
また、そこでは、共同体の中で自らにあたえられた社会的な地位や関係を実質的に所与の条件として受け容れて生きていくことが「常識的」な生き方として選択されることになる。即ち、物語や神話を共有する仲間達と集いあい、その輪の中に留まることそのものが半ば自己目的化するのである。
また、この発達段階においては、この作品にも描かれているように、同じ地域共同体の中でも、自らにあたえられた社会的・経済的な境遇を「宿命」として受け容れて、その「定め」に従って生きていくことが唯一の可能な生き方であるという想念にとり憑かれる傾向にある。
例えば、作品中、主人公の親友であるクリス・チェインバース(River Phoenix)は、そうした境遇の呪縛から逃れるために苦闘をする少年として描かれる。彼は、家族の面々がアルコール依存症という不幸な境遇のもとに生まれ、そのために共同体の中でも常に侮蔑のまなざしを向けられながら育ってきた少年であり、実際に学校でも窃盗事件を起こし停学処分にされるなど、荒んだ日々を送っている。
また、そうした状況に追い討ちを掛けるようにして、本来であれば、彼を庇護すべき存在であるはずの教師に裏切られ、心に深い傷を負ってしまっている。
この物語は、主人公のゴーディーの成長の物語であるだけでなく、その親友のクリスの成長の物語でもあるのである。
作品の終盤、成人した主人公によるナレイションを通して、視聴者は、Chrisが、そうした「宿命」の呪縛から逃れるために、その後懸命に勉強に励み、弁護士になったことを告げられるが、クリスのそうした生き様を思うと、順応型段階の葛藤といかに対峙することができるかということが、個人の人生にいかに大きな影響をもたらすことになるのかということが窺えるだろう。
正に自らにあたえられた理不尽な運命の重圧のもとに苦悩し、そして、そうした運命に抗うために格闘することができるかどうかということが、ひとりの個として自己に付与された可能性を開花させることができるか否かに影響をあたえるのである。
ここには、個としての人格を確立する内的な変容の旅において、真に悩む力こそが成長に向けた必須の条件であることが明確に示されているといえるだろう。
人生の理不尽さに憤り、悲しみ、悩む力こそが、そして、そうしたものを克服していける力が自己の内に息づいていることを信じる力こそが、こうした発達の橋を渡るためには必要になるのである。
いうまでもなく、こうした自己の勁さを「発見」するためには、そうした資質を自己の中に見出してくれる他者の存在とまなざしが必要になる。
この『スタンド・バイ・ミー』という作品の魅力とは、そうしたまなざしに触れる体験が、その後の長きにわたる人生を通してわれわれを心の奥底で支えてくれる懸け替えのないものであることをゴーディーとクリスという二人の少年の関係の中に結晶化させているところにあるといえるだろう。
発達心理学者は、人間の成長というものが常に関係性の中で展開していくものであることを指摘するが、この作品を観ると、他者のまなざしの中に籠められた想い――それは信頼や尊重かもしれないし、あるいは、軽蔑や侮蔑かもしれない――がわれわれの存在にもたらす影響の圧倒的な重要性を痛感せざるをえない。
とりわけ、順応型段階を超えていく過程においては、それまでにあたえられたものとは質的に大きく異なる支援が必要になる。
即ち、ユニークな個人としての自己の中に息づく才能や資質を見抜き、その価値を承認する他者のまなざしが必要となるのである。正にそれは決して大袈裟ではなく「愛」という言葉の最も本質的な意味を体現するまなざしといえるだろう。そして、ゴーディーとクリスの関係がどこか恋愛関係を想起させるのは、そこにまぎれもなく愛が息づいているからなのだろう。
ところで、この作品の素晴らしいところは、同時に、順応型段階の世界観により支えられる人間関係の呪縛から自由になることがいかに難しいかということを描いているところである。
エイス・メリル(Kiefer Sutherland)に率いられる不良少年達は正にそうした重要な試練に敗北をした者達の絶望と怨念を体現する登場人物といえるだろう。その姿は、あたえられた境遇を変えようのない宿命として受容することを強いられ、その鬱屈を刹那的な快楽と暴力的な行動として暴発させている姿のようにも思われるのである。しかし、それでは、そうした鬱屈を糧にして、彼等が自己を呪縛する宿命に抗うために自己陶冶にとりくむかといえば、そのような気配は全く無い。表層的には迸るような生命力を湛えているようにはみえるのだが、自己の存在を呪縛する亡霊に対して抗うことができるほどの勇気は持ち合わせていないのである。
彼等にできるのは、むしろ、そうした精神的な勁さをもつ年下の者達を目の敵にして虐めることができるだけなのである。
(また、彼等だけでなく、この作品の中で描かれる三日間の冒険を主人公と共にした二人の仲間――テディ・ドゥシャンプ(Corey Feldman)とヴァーン・テスィオ(Jerry O’Connell)――も、同じように自らにあたえられた宿命に絡めとられたままにその後の人生を生きていくことになることを作品の終了時のナレイションを通じて視聴者は教えられる。)
この発達段階の葛藤といかに対峙するかということは、個人の人生そのものに実に大きな影響をもたらすことになるのである。
このように眺めてみると、この郷愁溢れる物語の本質には、実は非常に残酷な人生に対する洞察が息づいているということができるだろう。
今日、いわゆる「成人発達理論」が注目を浴びるようになる中で成人期の内的な成長や発達に関する興味や関心が高まりつつあるが、実はそれまでの数十年にわたる人格形成のプロセスを通じて、われわれはいくつも重要な葛藤を経験し、それらに独自の答えを出してきているのである。
そして、われわれが成人期において直面することになる課題とは、結局のところ、そうしたプロセスを通じて築いてきた人格構造を基盤としてとりくまれることになるのである。
そこに蓄積された知識や知恵、そして、経験や能力を用いて――また、そこに温存された傷や病や歪みに囚われながら――われわれは新たな試練と向き合うことになるのである。
そうした意味では、成人期を迎えてより困難な課題や問題と対峙しようとするときにこそ、われわれは、それまでの人生を振り返り、それぞれの人生の季節において自身に衝きつけられた課題と対峙して、そこに何等かの答えを導きだしてきた過去の自己の格闘とその成果を再確認すべきなのだろう。
今回、実に久しぶりにこの作品を鑑賞したのだが、人生の後半を迎えた筆者の心の内に喚起された郷愁とは、実は単に少年時代を懐かしく回顧する感覚だけでないのかもしれないと思いはじめている。その感覚の中には、「少年時代」というものが、実はその後の長い人生を生きていくうえで途轍もなく重要な試練を衝きつける残酷な季節であるという厳然たる現実を認識する者として、そうした試練を受けて立つにはあまりにも未熟であった過去の自分に対して――そして、そうした状況の中で「勝ち目の無い」苦闘を強いられている全ての同胞に対して――感謝と応援の念を送ろうとする祈りの気持ちが息づいているように思えるのである。