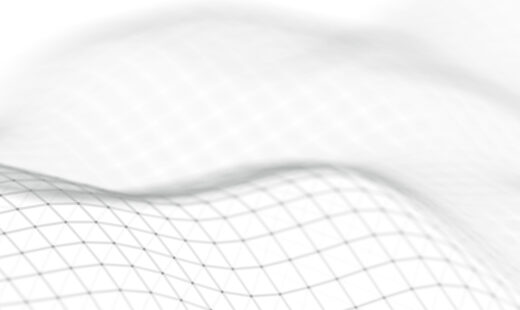成人発達論:取扱上の注意

「最も強い者が生き残るのではない。最も賢い者が生き残るのでもない。唯一生き残るのは変化できる者である」
改革や自助努力、闘いの勝利を期待する企業経営者や政治家、それに政権与党の広報などが大好きな言葉である。「ダーウィンの呪い」の象徴的存在と言える。だがこの言葉を使っている人の思惑とは裏腹に、実はこの言葉はダーウィンの言葉ではない。
千葉 聡(2023)『ダーウィンの呪い』 講談社 (P. 90)
対象とするクライアントの年齢を問わず、対人支援に携わる者にとり、「成長」・「発達」・「進化」という概念をいかに解釈するかという問いは非常に重要になる。
そうした概念をいかに解釈するかにより、支援者の実践が大きく変化することになるからである。
端的に言えば、それらの概念の解釈を誤ると、支援者は容易に優生学的発想に陥り、完全なる善意にもとづいて、識らず識らずのうちに人間の尊厳を蹂躙するようなことをしてしまうことになるのである。
特に近年ひろく注目を集めている「成人発達理論」に興味・関心を寄せている者にとっては、これは最も重要な検討課題のひとつであるといえる。
成人発達理論の文脈においては、クライアントが社会的・経済的な活動に従事する成人であるために、人間の成長・発達は常にその実利的な価値と密接に繋げられて扱われることになる。
端的に言えば、「成長や発達をすることは、今日の経済システムにおける市場価値(価値創造能力)を高めることに寄与するのか?」という問いに恒常的に晒されることになるのである。
たとえば、成人発達理論を組織運営に応用したこころみのひとつである「ティール理論」は、正に「組織を発達させることがその価値創造能力を高めることに貢献する」という物語に立脚したものといえるが、そこでは、「成長」「発達」というものが所与の社会的制度や体制の中で求められる機能や能力を向上させるものとして解釈される傾向にある。
換言すれば、その発想は次のようにまとめることができるだろう。
「急激に変化している現代社会に適応し、そこで顧客に選ばれる企業としてありつづけるためには、卓越した能力を獲得する必要がある。そして、それらの能力こそがティール段階の能力なのである」
しかし、ここでわれわれが注意すべきは、こうした発想が、基本的には、われわれが前提とする価値観や世界観を前提とした成長や発達の物語にもとづいて「期待される能力」を構想していることである。
そこでは半ば必然的にわれわれの意識を呪縛する価値観や世界観の投影が起ることになる。
「今後 期待される人物像や組織像」とは、今われわれが生きているこの世界の延長線上にある未来の世界の中でわれわれの生存可能性を高めてくれる諸々の能力を要素として構想されることになるのである。
しかし、そうした一連の思考そのものは、今日の社会の価値観や世界観の形成に巨大な影響を及ぼす支配層の思惑を反映したものとならざるをえない。
思想家のユルゲン・ハバーマスは(Jurgen Habermas)は現代社会の特徴を「公共空間の再封建化」(”refeudalization of the public sphere”)という言葉で示したが(公共空間の中で営まれる言論活動は、報道機関や研究機関や教育機関や情報網をはじめとする諸々の社会的な装置を通して営まれるが、それが非常に少数の富豪により占有され、表面的には言論の自由が保障されているようにみえるが、実際には巧妙に言論活動が制限・操作されている状況を示す概念)、現代社会のようにごく少数の人間や組織に富の集中が極度に高まり寡頭制が極端に進展した社会においては、そうした傾向は不可避的に高まることになるだろう。
即ち、期待される人間像や組織像は、現代社会の支配構造を維持・強化する方向で構想され、また、そのために都合のいい能力が美化され、そしてそれを開発するためのとりくみが奨励されることになるである。
また、そうした能力の開発度を測定するための様々な測定が用意され、外的な期待に沿って能力開発に従順に勤しむ態度がひろく涵養されていくことになる。
実際、今日、「ティール・ムーヴメント」の傘のもとで様々な善意の活動が展開されているが、そこで、上記のハバーマス問題意識を継承して、富の一極集中をはじめとする真に重要な構造的な問題に対して問題提起をしているものは非常に少ない。
大多数は、あくまでも現代社会の中であたえられている構造の枠組の中で組織が生存・発展していくための方法を探求したり、あるいは、そうした構造の持続可能性を高めていくための方法を模索したりするものに留まっているのである。
実際、ティール的発想の重要要件として、人類社会の支配構造そのものに目を向けて、その構造そのものを変化・変容させるための批判的な精神やスキルや態度を涵養することが指摘されることはほとんど無い。
われわれは同時代の支配的な価値観や世界観の呪縛から完全に自由になることはできない。
それゆえに、みずからの生きる社会で信奉される物語に絡めとられ、その文脈で称揚される徳を開発することに夢中になってしまう。
そうした文脈の中では、成長や発達という概念はあまりにも容易に社会の支配的なイデオロギーを維持・強化し、また、そこに存在する支配構造を肯定するための道具に成り果てる危険性を秘めている。
20世紀においては、それは、国を強靭化するために貢献できる人材としての能力を意味していた。
そして、21世紀においては、それは人類社会の持続可能性を高めるために貢献できる人材としての能力を意味する。
いずれも、一見すると真当なものに思われるがーー特にその時代の空気の中でそれらは正に正義を体現するものとみなされることだろうーーしかし、少し醒めて眺めてみれば、そこには本質的な意味で個を集合体(collective)の構成要因として位置づけ、その使命を集合体に貢献・奉仕することに見出す全体主義的発想が厳然と息づいていることに気づくだろう。
また、そうした発想が先鋭化するときには、全体性に貢献できない存在をーー全体性を弱体化する存在をーー矯正や排除や処分の対象としてみなす発想が市民権を得ることにもなる(歴史的に人類社会の深層に息づく優生主義的衝動は、それが顕在化するための条件が整うと瞬時に社会の表舞台にあらわれ人々を呪縛することになる)。
そうした状況においては、成長や発達という概念はーーまた、それを把握するための測定はーーそうした矯正や排除や処分を正当化するための道具になりえるのである。
フーコー(Michel Foucault)をはじめとする思想家達が指摘するように、「正常」と「異常」を分類するための道具として用いられる医療的な診断はしばしば人間の尊厳を踏みにじる暴力装置となりえるが、正に、成長や発達の度合いを把握するための心理測定は、所与の価値観や世界観に対する従順性や適応性を測るための道具となりえるのである。
そして、それはそのままその時代を支配するイデオロギーを実現するために都合のいい「正常者」とそうでない「異常者」を分類するための道具になりえるのである。
結局、「適」と「不適」は、権力者や意思決定に関わる者の偏見や差別や利害関係による選別でしかない。この目的ゆえに19世紀以降の優生学は、社会的な格差・文壇による社会問題を、偏見・差別を動機に効率的かつ安易に解決したいという野心を実現する手段となった。この目的のため、生物進化と定量的な説明を使って偏見・差別に真理の仮装を施し、社会に強制し、人々を操り、これで人々を悩ませてきた問題が解決できると信じさせた。これこそが惨劇を招く元凶となった誤りである。
千葉 聡(2023)『ダーウィンの呪い』 講談社 (P. 277)
その性格上――たとえば過去にIQがそのように用いられたようにーー成人発達理論も、同時代の支配構造や利害関係を維持・強化するために用いられる危険性と隣り合わせに存在している。
とりわけ、巷の解説書にあるように、高次の発達段階が、人類の公共的な利益のために高い倫理観にもとづいて貢献できる能力に特徴づけられたものとして示されるとき、そうした高邁な精神をもつ人々の善意は、発達を善性に向けたプロセスとして単純化してとらえて、そうした発達のプロセスを歩むことを他者に強要する原理主義的な発想に囚われてしまいがちになる。
また、そこでは、そうした能力を習得しているとされる高次の発達段階に到達した人々を特権化する歪なエリート主義が蔓延することになる可能性もあるだろう(たとえば、こうした可能性は、自己を「Teal段階」に到達していると判断した人が他者に対して成長・発達をするように迫る光景に顕在化している)。
今日、人類社会は「Sustainable Development Goals」をはじめとする麗しい標語で仮装して推進される「Great Reset」の荒波に晒されているが、われわれが冷静に注視すべきは、そうした「改革」が、World Economic Forumに象徴される超富裕層を頂点にいだく今日の寡頭制の維持と強化に資するものとして設計・展開されているということである。
そして、そうした麗しい物語に共感して、その実現に貢献しようとする姿勢は、そのあまりの無防備性(naivete)ゆえに、よういにそうした体制の思惑に呑み込まれてしまうことになるのである。
人間の成長や発達というものが、社会価値観や世界観と紐づけられ、そこで「成功」や「勝利」の象徴として崇められている「像」と同一視されるとき、発達理論は、そうした像に向けて修練をするように個人の尻を叩く強圧的な装置に転じることになる。
そのとき発達理論は、そうした所与の目標に向けて少しでも効果的・効率的に前進するように個人を彫像していくための装置になるのである。
そして、そうした状況の性質に無意識であるとき、支援者は容易に同時代の支配構造を維持・強化に加担する者に堕してしまうのである。
人間の成長・発達とは、あらかじめ定められた目標に向けて前進していくプロセスではない。
また、個人が生きる時代や社会の中で、その構成員として求められる能力を従順に習得するだけのプロセスでもない。
人間の成長や発達がそのようなものとしてとらえられてしまった瞬間、そこに内在する創造性の芽は摘み取られてしまうことになるのである。
先日、発達心理学者のTheo Dawson博士が主宰するトレイニングに参加していた折、彼女が非常に興味深い発言をしていた。
われわれがLectica, Inc.でしようとしているのは、人間の発達というものを「目的論」(teleology)の呪縛から解き放つことである。
これは果たしてどういう意味だろうか?
「成人発達理論」に関心を寄せる人々は、しばしば、人間の成長・発達というものをなんらかの定められたゴールに向けて展開するプロセスとしてとらえがちである。
たとえば、「……段階に到達すると……ができるようになる」とか、「……段階に到達すると……という発想をするようになる」という風に、高次の発達段階にみずからの希望や期待や理想を投影して、人間の成長や発達というものをそこに向けて展開するプロセスとしてとらえるのである。
先述の「ティール・ムーヴメント」などは、そうした目的論に呪縛された発想の代表的な例といえるだろう。
生物学的な進化の意味は、遺伝する性質の世代を超えた変化である。生物進化は一定方向への変化を意味しない。目的も目標も、一切ないのだ。
千葉 聡(2023)『ダーウィンの呪い』 講談社 (P. 12)
自然選択は、動植物の育種のため人間が行う変異の選抜――人為選択がヒントになっている。だが人為選択と異なり、自然の作用には育種家が抱くような変化の目的や目標はない。ダーウィンにとって、どのような変異が生じるかはランダムであり、どのような性質が有利かは環境によって変わるので、進化は条件次第でどのような方向にも進みうるものだった。つまり進化には発展や進歩のような、あらかじめ定まった方向はない。退化も進化である。
千葉 聡(2023)『ダーウィンの呪い』 講談社 (P. 13)
これらは、チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)が、生物界の進化に関して述べたことをまとめた文章である。
われわれはしばしば「進化」を「進歩」や「発展」と混同してしまう。
往々にして、われわれは進化をするとは、「VUCA」とも形容される今日の人類社会に適応しながら、そこで地球規模で展開される経済競争の中で存在価値を発揮しつづけることだと解釈しているのである。
そして、そうした解釈の枠組の中で人間の「成長」や「発達」という概念もそうした適応に直接的に寄与するものとして意味づけされるのである。
われわれが発達理論に投影している「目的論」(teleology)とは即ちそうしたものである。
成長・発達とは、このVUCAと形容される社会の中で展開される経済競争で常に価値を生み出し勝者でありつづけることを可能とする条件である。成長・発達は、そうした可能性を最大化してくれるのである……
われわれ現代人を呪縛する目的論とは、こうした価値観にまとめることができるだろう。
成人発達論を扱う者として、われわれが留意すべきは、こうした価値観を無意識化したままで成長や発達という概念を扱うことの危険性である。
それは、非常に限定的な時代的・社会的な文脈の中で成立する基準にもとづいて人間の価値を測定して、垂直的に序列化する発想を鼓舞することになる。
そして、それはおのずと「望ましい」資質や能力を有している者を優遇し、「望ましくない」資質や能力を有している者を排除する態度を生み出すことになる。
いわゆる優生学的発想を正当化することになってしまうのである。
Theo Dawson博士が「人間の発達を目的論(teleology)の呪縛から解き放ちたい」と述べる背景には、このような問題意識があるのである。
限定的な時代的・社会的な文脈の中で信奉される大きな物語にもとづいて、そこで高く評価される資質や能力を恣意的に高次の発達段階の特性と位置付けて、人間の成長や発達そのものをそれらの特性を体得するためのプロセスとして見做すこと――
成人発達理論の関係者はこの陥穽に警戒する必要があるのである。